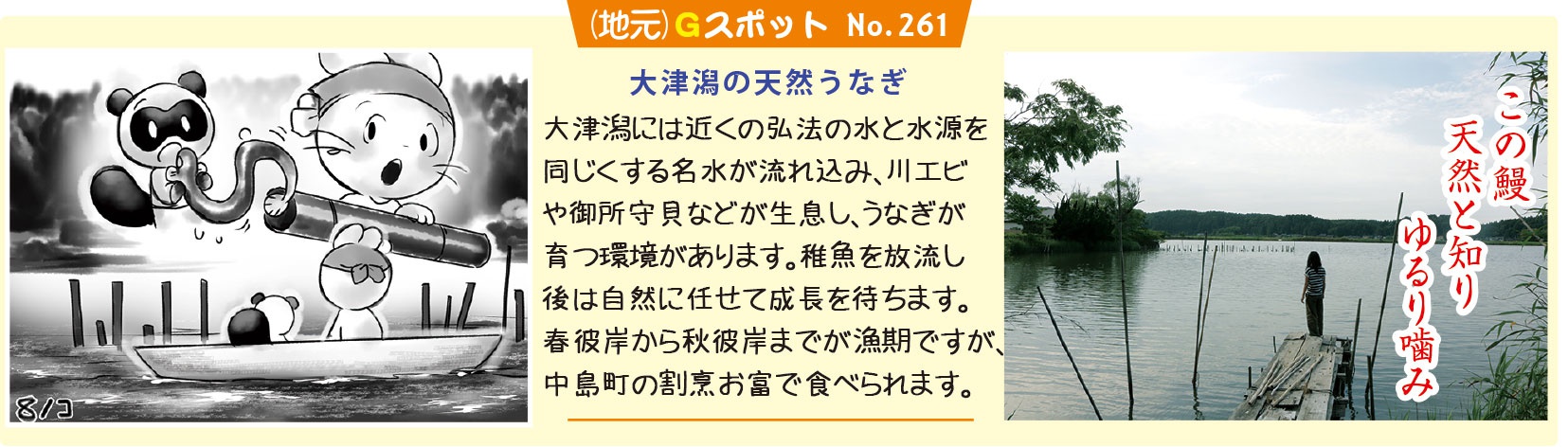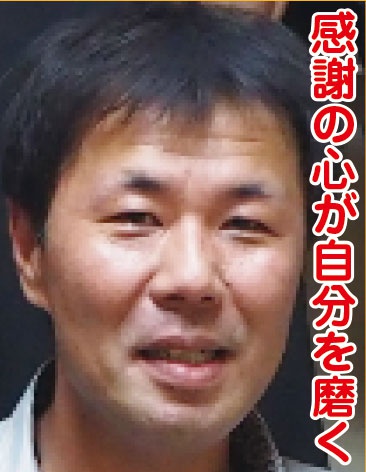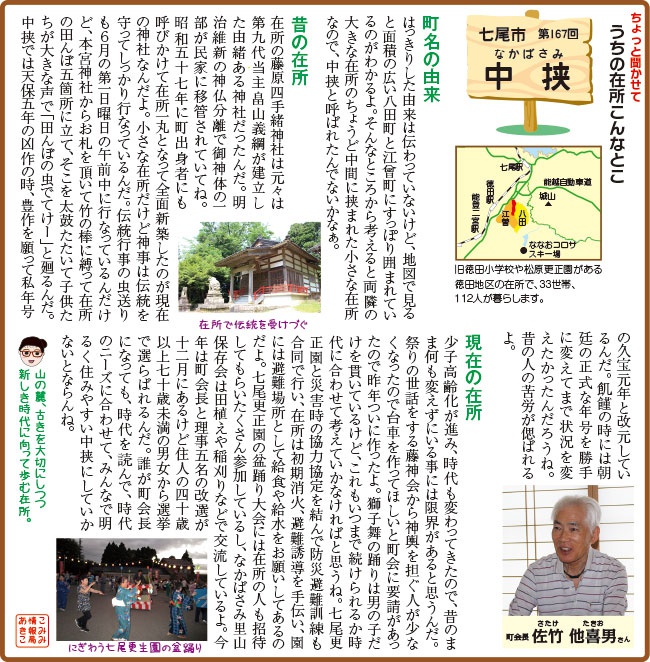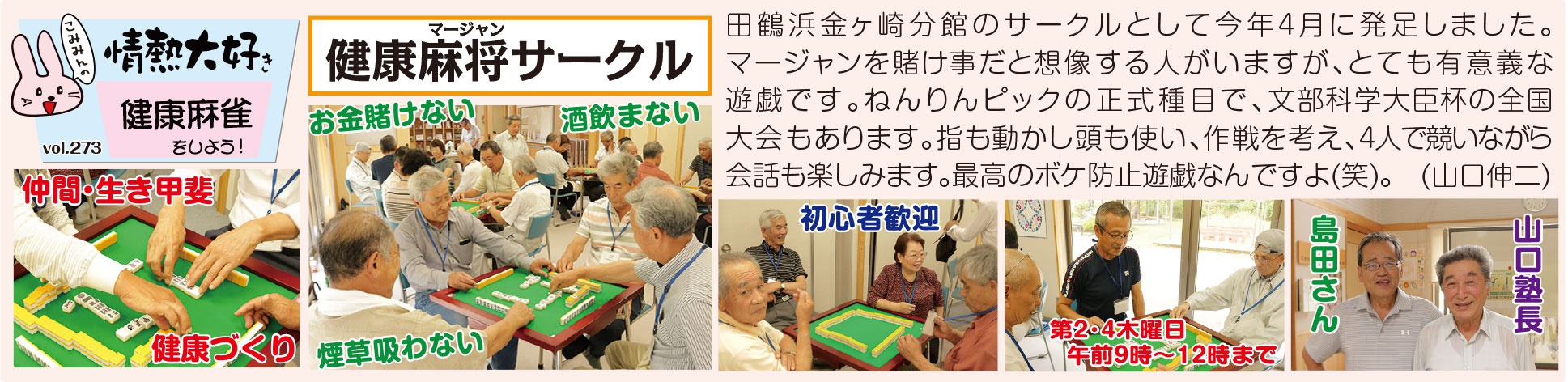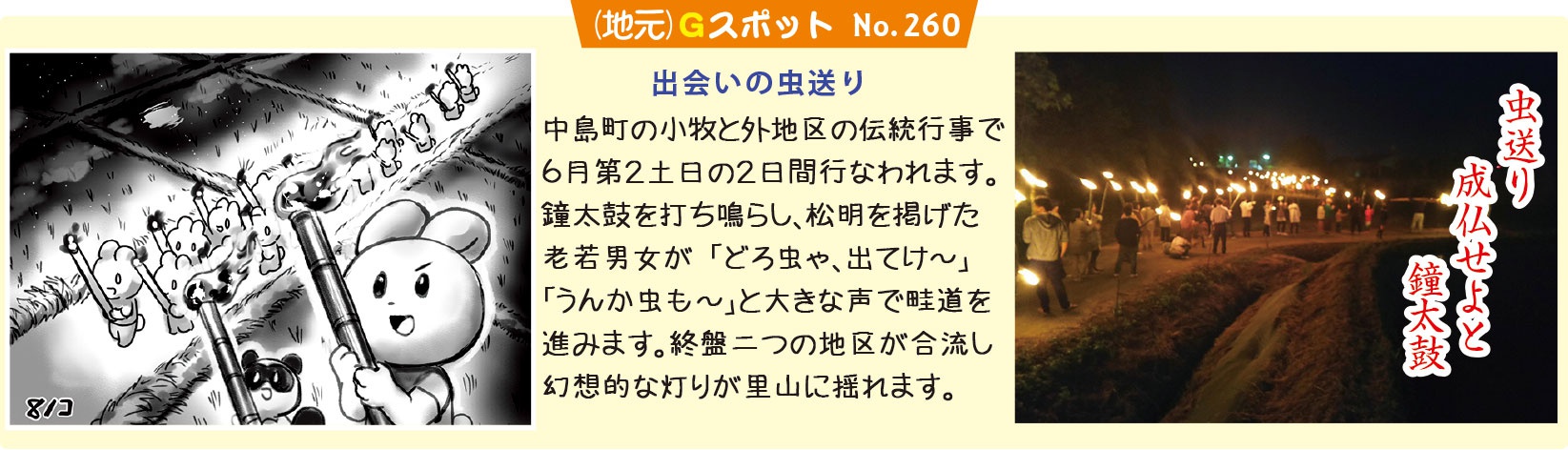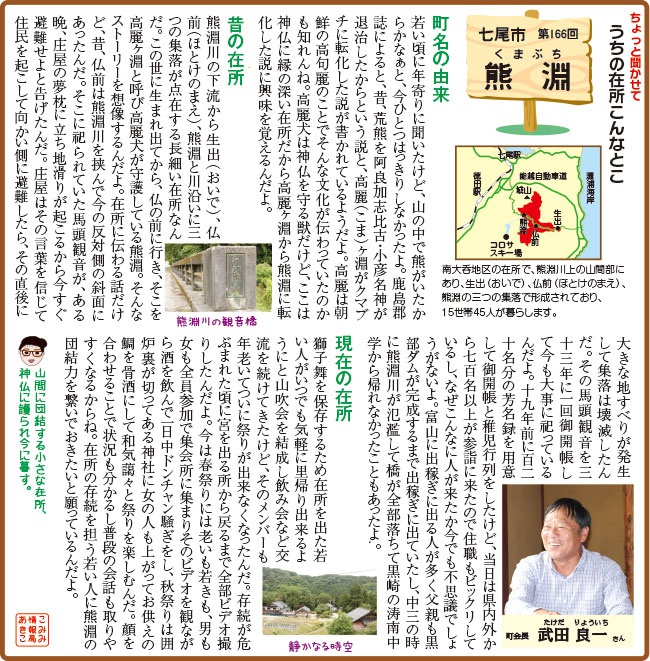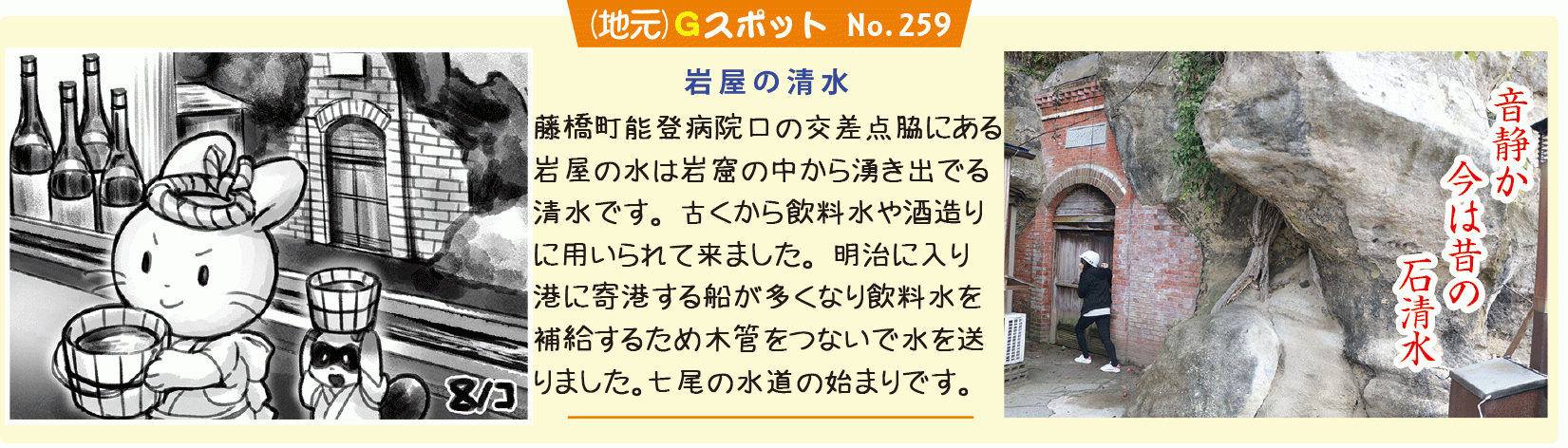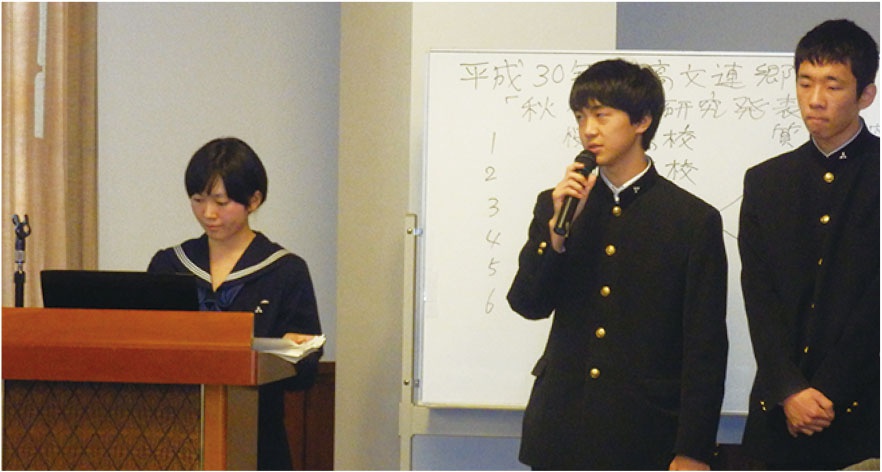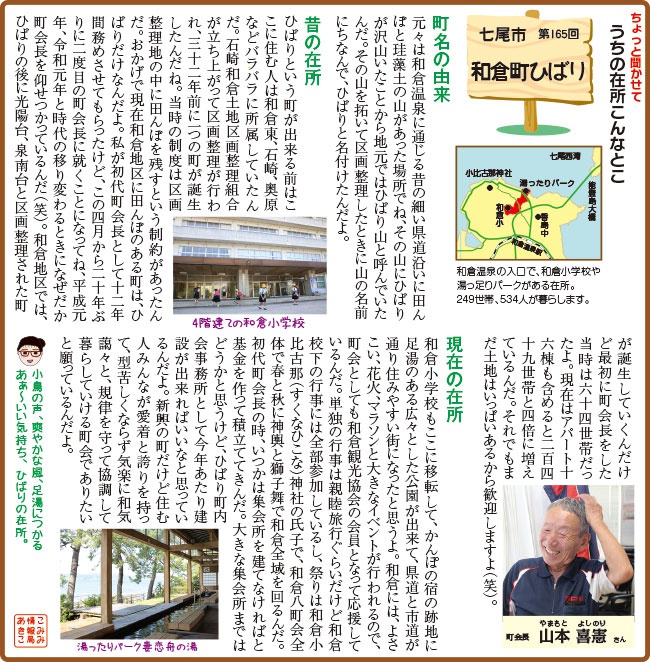第46回 「輝け!郷土の星」走高跳の亀田 実咲さん(鵬学園2年)
石川県総体優勝・北信越総体3位入賞
5月の県総体1m66で優勝、6月の北信越総体1m67で3位入賞、インターハイ出場を決めた実咲さん。インターハイでどんなジャンプを見せてくれるのか期待が高まります。
実は実咲さん、宇ノ気中学3年生の時にジュニアオリンピックで1m70を飛んで全国チャンピオンになっている期待の選手です。走高跳を始めたキッカケは中学時代に体力をつけたいと陸上部に入部。
最初は短距離を始めますが、なぜだか「走高跳したいなぁ~」と思いが募ったそうです。
小学生の時から、跳んだりはねたりして、落ち着きの無い子だと言われていたので、跳ぶことが好きだったのかもしれませんね。と可愛く笑う実咲さんですが、話を聞いていくと驚きの事実が…! 父方の祖母、母方の祖母、二人のおばあちゃんが走高跳の選手だったのです。
実咲さんはその事を後になって知ったそうです。こんな偶然があるのかと思いますが、だからこその必然だったのかもしれません。
鵬学園陸上部
進路を星稜高校陸上部と考えていましたが、競技会などで顔を合わせていた1年先輩で羽咋中の麻生京花さんが鵬学園で走高跳をしており、ここは一人一人にしっかり指導してくれるので良いよと誘われ、鵬学園に進学しました。
部員は男子5名、女子8名の少数精鋭の陸上部ですが、今春の県総体では3年生の麻生京花さんが走高跳で3位、宮脇愛果さんも走幅跳で3位、2年生の浜辺ひかりさんが400mで4位と活躍しています。1年生の時は自分の事でいっぱいでしたが、2年生になって後輩に声をかけチーム全体の事を考え、明確な目標も口にできるようになった実咲さん。
島元コーチは身体能力がまだ全体的に低いので、3年間で結果を求めるのでなく、7年スパンでのパフォーマンスに期待したいと話します。

さすが!みんな足が長い!!
走高跳
中1で1m45、中2で1m60、中3で1m70と順調に記録を伸ばしてきましたが、高校に入り自己ベストを更新できていません。走高跳はひじょうに繊細な競技で、スタート位置、歩幅、踏切位置、助走のスピード、リズム、跳ぶフォーム、全てがオリジナルです。
ビデオ撮影して、これで跳べた、これで跳べなかったと原因を探り、自分の型を探りながら確立していきます。今日はこれで良いとイメージしても、高校生の身体は日々成長していくので、そこにまた微妙なズレが生じます。
実咲さんは100mが14秒台から13秒台になり助走も力強くなりましたが、その勢いを跳躍にどう活かすか研究中です。練習は城山グランドで行ないますが、毎日跳ぶと逆にバネが無くなるので大会スケジュールに合わせて週1回から3回と調整しています。
何より跳ぶことが楽しいと思っている実咲さん、今井監督や島元コーチの時に厳しい言葉も総べて自分のために言ってもらっていると素直に受け止めます。走高跳で辛いと思ったことは無いと言い切り、 「1m75、日本一!」 と明確な旗を立て、「大ジャンプします!」 と取材を締めてくれた。あっぱれ!

精鋭!鵬 陸上部